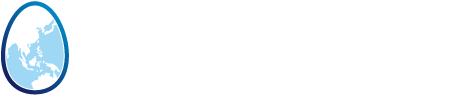Newsletter
Newsletter
AI NEWSLETTER Vol.61 「どうすれば人は育ちますか?」ーリーダーに共通する5つの価値観
2025年1月28日「どうすれば人は育ちますか?」― 私たちが日々いただくご相談は、本質的にはこの1点に集約されます。
人間は環境や経験によって変化していく生き物ですから、上司や会社の関わり方が重要なのは間違いありませんが、一方で、人間は機械ではないので「このボタンを押したら、こう育つ」といったほどシンプルなものではなく、単純明快な解はありません。
ですが、共通点はあります。
「リーダーがどんな価値観で相手を見ているか」。
これによって、人材育成の結果は大きく変わります。多くの優れたリーダーを観察していると、そこには共通した姿勢があるように感じます。
本コラムでは、そのスタンスを支えるいくつかの観点を具体的に紹介します。

1. 「できない」ではなく「まだ・できていない」と考える
リーダーによっては、成果の出ない部下に「こいつはできないやつだ」と早期に判断してしまうことがあるでしょう。しかし、成長を促すリーダーは「できない」ではなく「“まだ” できていない」という考え方を大切にします。
この違いは言葉尻のようでいて、部下の未来を諦めるかどうかの大きな分かれ道になります。「できない」と言い切ってしまえば、今後もその人に期待はしないという結論になります。その発言の裏側にある心情を部下は(特に表情や言い方などから)敏感に感じ取り、「あの人は自分をもうあきらめたんだな」と受け取ります。一方、「“まだ” できていない」という態度で接すれば、もう一度チャンスを与えたり、サポートのやり方を変えてみたりと、成長するための双方の試行錯誤に繋がります。
2. 「何か理由があったんだろう」と考える
例えば何か部下がミスをしたとすると、多くの上司は「あれだけ教えたのに」「こんなこともできないのか」と、相手を責めたくなる気持ちを持ちます。しかし、人材育成に長けたリーダーは、相手の行動には必ず何か理由があると考えます。これは、部下の行動を全肯定するという意味ではなく、まずは「なぜそうなったのか」を丁寧に拾い上げようとする姿勢です。
例えば、新しいプロジェクトで期日が守れなかったときに、「怠惰だから」「彼はミスが多いから」という一方的な断定をするのではなく、「こんなミスをするなんて彼らしくない」「リソースが足りなかったのかもしれない」「家庭の事情で時間が取れなかったのかもしれない」など、「隠れた理由」を想像するわけです。そのうえで、直接ヒアリングしてみると、本人も思い悩んでいたり、想定外のトラブルに遭遇していたりすることがわかるかもしれません。
もちろん、「隠れた理由」などなく「単に怠惰だった」という事もあるでしょう。その場合は、適切な指導や注意喚起が必要です。ですが、人間は直観的に、自分の解釈したいように物事を判断したい生き物なので、しばしば早期に「一方的な断罪」をしがちであるという事を心得ておきましょう。
3. 「人を憎む」のではなく「問題を憎む」
問題を解決する際には、「人を憎む」のではなく「問題を憎む」というアプローチを取ります。
例えばミスを繰り返す人がいたとして、「どうしてあなたはミスばかりするんだ」と個人攻撃をされると、本人のモチベーションは上がるどころかむしろ下がり、ミスの解決は遠ざかります。そうではなく、「どうしたらミスが無くなるか、一緒に考えよう」というアプローチを取ることで、個人攻撃を避け、建設的な対策を検討することができます。
人が育てられないリーダーは、本人の「人間性」に問題を帰結させます。「彼は主体性が低い」「熱意が足りない」などの表現を用いがちです。こうした人間性を標的にするのは「人を憎む」というアプローチで、あまり効果的ではありません。「熱意を出せ」と言われても、大抵の場合はどうしてよいかわからず、何も変化は起きないからです。合理的な解決策を取らず、精神論で問題を解決しようとするのは未熟なマネージャーです。

4. 強みと弱みは表裏一体だと捉える
私たちはしばしば、他人に対して「ここがダメだ」「ここが弱点だ」とネガティブな評価を下しがちです。ところが、実は人間の強みと弱みは表裏一体であり、どちらか一方だけが存在するわけではありません。例えば、「慎重すぎる」という弱みは、「じっくりと考え、ミスを減らせる」という強みにもなります。また、「スピードが遅い」という弱みは、「落ち着いて丁寧な作業ができる」という強みに裏返すことができるかもしれません。
人を育てるリーダーは、この視点を忘れません。一見すると「短所」に見える部分も、見方や状況次第で「長所」へと変わりうると考え、上手に活かそうとします。「もう少しスピードを上げて取り組む必要はあるが、あなたの丁寧さはチームにとって貴重だよ」といった伝え方をすれば、本人の自己肯定感を損なわずに、改善意欲を高めることができます。
こうした姿勢によって、部下は「自分は見捨てられていない」という安心感を持ちつつ、弱みを克服するために前向きに努力しやすくなるのです。ここでも大切なのは、相手には必ず成長できる強みがあると信じ続けることです。
5. 改善点をストレートに伝える
ここまで読んできて「そんなに優しい上司で良いのか」と思われたかもしれません。もちろん、何でもかんでも褒めてばかり、受け止めてばかりではいけません。改善点や問題点を直視し、真摯に伝えることも重要です。
人が育つリーダーは、多くの場合「仕事に厳しい」という印象を持たれています。「言うべきことを溜め込むのではなく、ストレートに伝える」スキルも必要です。ただし、いくつかの注意点はあります。
・伝え方が8割:「言い方」にメッセージはこもります。感情的な言い方はNGです。具体的な事例や数字、観察された行動を冷静に指摘しましょう。そのためにはリーダー自身のメンタルの安定性がカギとなります。怒りっぽいリーダーは何かしら自分自身に満たされなさを感じており、それを部下にぶつけてしまっているのです。
・タイミングも超重要:毎日のお天気に変化があるように、人間の気持ちも日々変わります。相手の精神が落ち着いていて、受け止められるタイミングを見計らいましょう。逆に、相手が落ち込んでいるとき、精神がいっぱいいっぱいの時にフィードバックをするのは、大抵うまくいきません。雨の日にピクニックに出かけるようなものです。
・「ロープの長さ」のコントロール:成長のためにはアドバイスやヒントが必要ですが、そのボリュームのコントロールが必要です。経験の浅い人にはたくさんのアドバイスが必要ですが、経験のある人は助けを最低限にしないと、自分で仕事をする力が付きません。自分の力で崖から這い上がれるだけの長さのロープを提供しましょう。
*タイ語版はこちらです。ぜひご同僚のタイ人の方にもシェアをお願いします!こちらです。
*日本人、タイ人のマネージャー育成のための公開コースのご案内はこちらです。
-

中村 勝裕(NAKAMURA KATSUHIRO)
Profile
CEO & Founder, Asian Identity Co., Ltd. “バンコクを起点にアジアに特化した人事・コンサルティングファームAsian Identityを経営。
ネスレ、リンク & モチベーション、グロービスを経て現職。
現在はタイを拠点としながら「多様性の調和」をミッションに掲げ、アジア各国でのコンサルティングや講演活動を手がける。
バンコクにおいてタイ人向けビジネス漫画「Su Su Pim! (がんばれピム!)」を執筆、販売。
アジア流のリーダーシップを提唱する『リーダーの悩みはすべて東洋思想で解決できる』(WAVE出版)を出版。”– Certified Facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY®
– Completed ORSC™ – Organization and Relationship System Coaching Practical Application Course
– Certified Facilitator of Hofstede Insight Organizational Culture (วัฒนธรรมองค์กร)
– CoachingOurselves Facilitator
Continue reading
-

19 2月, 2021
Newsletter AI NEWSLETTER Vol.45 「継続的に成果を挙げる」マネージャーになるための5つのステージ
AIニュースレター、45号です。 これを読んでいるビジネスパ… -

24 4月, 2018
Newsletter AI NEWSLETTER Vol.13 異文化環境のコンフリクトに対応する
今回のテーマは「異文化」です。といってもタイの文化、日本の文… -

10 7月, 2023
Newsletter AI NEWSLETTER Vol.55 「東洋的なリーダーシップについて考える②中庸なリーダーとは」
AIニュースレター、55号です。 前回に引き続き、「東洋的(…