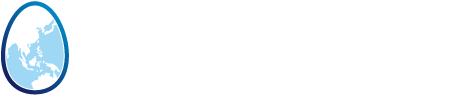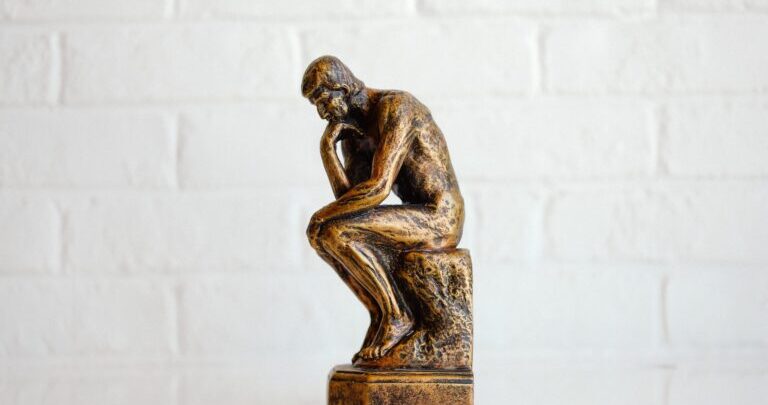 HR Blog
HR Blog
考える力を育てるために必要な「知的な躓き」とは
2022年5月25日先日、子供が通っている日本の中学校の保護者会に行ってきました。とても気づきの多い時間でした。
とても授業がユニークで、最近流行りのいわゆる「探求型」の答えを教えない授業をやっています。
例えば数学なら計算問題のようなものは殆どやらずに、その代わりに「この公式はなぜできたのか」「この公式は本当に正しいのか」など、数式の裏側にあることを問いかけ、考えさせ、ディスカッションをします。
教材を見ていると親から見てもとても難解に見え、ともすると哲学的な授業のようです。およそ中1、中2でやることのようには見えません。
まだまだ実験的な取り組みということもあって、保護者会に参加される親御さんには不安の様子が一部あり、質疑応答では質問がたくさん出ました。
「一般的な模擬試験では他校よりもずいぶん平均点が低かった。受験勉強とかけ離れてしまって本当に大丈夫なのか」
「考える力を伸ばすのはわかるが、何をやっているのか親もわからず、家で勉強を教えてあげることもできない」など。。。
それに対して先生方から説明があったのですが、それはとても覚悟を帯びたものでした。
まず、受験対策をして一流校に入った生徒を見ていると、大学で躓く人が少なくないということでした。
例えば数学が好きで数学科に入る人のうち、10%くらいしか大学の数学についていけないのだと。なぜなら、高校までの数学は試験対策であり、ある意味で答えを見つけるゲーム。しかし大学からは「数学は哲学になる」と言われていて、自ら問いを立てて本質を考え抜く力がないと数学を研究できない。しかし受験対策だけやってきた生徒が大学からそれを身に着けるのは簡単ではなく、挫折してしまう生徒が少なくないのだとか。
同様のことはほかの分野にもあり、例えば音楽科などでもそうだと。決められたことに従うレッスンを厳しく受けてきた生徒は、大学に入るとそれ以上演奏家として伸びなくなる。自分で課題を見つけて克服していく力が低いと、あとからそれを身につけるのは難しいのだと。
「答えのない問いを考える」ことの困難さと、その大切さになるべく早く気付かせないといけないんです、と先生方は強調しました。
そしてそのために必要なのは「知的に挫折し、そこから立ち上がる経験」なのだと。
大学生になってからその挫折を初めて経験するのではなく、むしろ中学生で経験させておきたい。早く壁にぶち当たれば、自分の力で壁を乗り越える経験をすることができる。だから、答え探しのドリルを解いたりすることに、時間を使わせたくないのですと。(もちろん受験勉強でも考える力を伸ばせるとも思いますので、あくまでやり方次第だとは思います。)
これは大人の人材育成にも通じるなと思いました。
「答えを教えることは本人の主体性を奪う」という考え方があります。「すべて上司が教えてくれる」という前提でなんでもかんでも教えてしまうと、意外と部下は育ちません。
上司はヒントは与えるけれど、そこから先は自分で考える。適度に自分で苦しみながら、自分の手で答えをつかみ取ってもらう経験も、人材育成上はとても重要なことです。
そうはいっても、保護者から懸念をぶつけられながらこうした信念を貫くのは簡単ではないと思います。それでもこの先生たちは覚悟を持ってやっているんだということを自分は感じました。
この先生方はまだ30歳そこそこの、若手と呼んでも差し支えない年齢です。にもかかわらず、こうした挑戦心を持って教育に臨んでいる姿勢に触れられたことに感動し、改めてそんな環境での子供の成長を見守っていきたいなと思ったのでした。