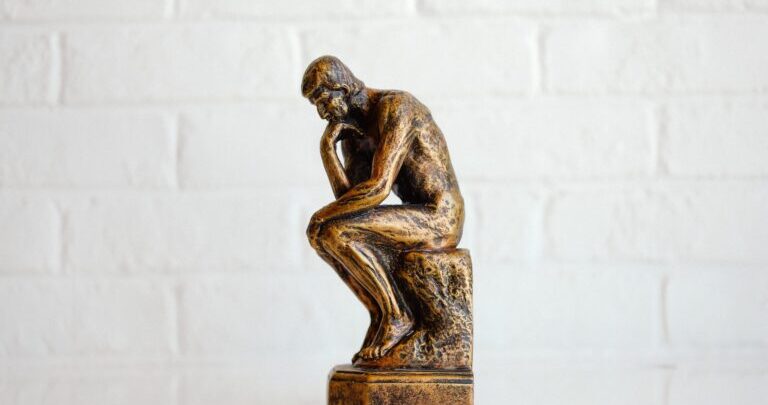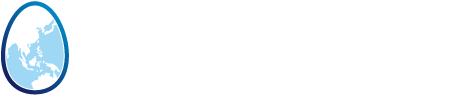HR Blog
HR Blog
涵養(かんよう)という優しさ
2020年5月21日涵養(かんよう)という言葉を知ったのは、今年に入ってからでした。日本に帰国した際に母から手渡された本にあった言葉です。奈良少年刑務所にいた少年たちの詩集。
「あふれでたのはやさしさだった」
「空が青いから、白をえらんだのです」などが代表的な詩集です。
涵養のもともとの意味は「水が自然に染み込むように、無理をしないでゆっくりと養い育てること。」
2016年まで存在していた奈良少年刑務所の受刑者の少年たちに施されていた社会性涵養プログラムというものがあります。
童話作家の寮美千子さんが講師を務め、受刑者の少年たちに自分の感情や思いを表現していく授業を行いました。更正のための反省文を書くのではなく、詩、というかたちを通じて自分の思いを表現する練習をするのです。
何を言ってもどう在っても「安心・安全な場」として自分の感情や思いを表現できる場。
良し・悪しで評価されるのではなく、ただ受け入れられる、そんな場です。
「ヒトのこころにはかならず良き種が眠っていて環境が整えば、自分から光に向かって伸びていく。その大切な場が安全・安心な場です。」
奈良少年刑務所の当時の受刑者の平均年齢は20代前半。彼らは何らかの許されがたい罪を犯し、服役・更正のために刑務所に入っていました。加害者である前に被害者であった、と表現される彼ら。できない子、何をしても無理な子、排除されてきた子、鬱屈した行き場のない感情が爆発し、犯罪につながった。
感情の表現や思いの伝え方が分からない。そもそもそれをオープンにすることを許されなかった子たちはいろんなものに失望していったのです。
プログラムを経る中で、彼らは自分の思いを言葉にしていきます。
どもりの子がどもらなくなり、誰とも会話できない子が話せるようになり、偉そうにふんぞり返った態度しかとれなかった子が膝を揃えて座るようになり、他の受刑者の聞き役になったり。
受刑者の少年たちはこのプログラムを通じ、深い気づきや変容を引き起こしていきます。
自分の思いを言葉にし、表現し、それを共有すること。
人によっては簡単なことかもしれませんが、彼らが思いを言葉にする勇気は計り知れません。
ただ、彼らは言葉にして共有するという過程を経て自分というものを知り、そして変わっていく。共有し、ただ受け入れられるという経験を経るだけで人は変わるのだという事実をこの詩集と寮美千子さんのプログラムは示しています。
最近はよく「心理的安全性」がチームのパフォーマンスを高めるうえで重要なファクターであり、リーダーやメンバーはその環境を作ることが重要だなどと言われます。
発言することに恐怖や不安を感じない、自分らしく働き、なんでも安心して言える環境においては建設的な議論が可能になる、ということです。
なれ合いとの境目、ただの仲良しチームにならないようにせねばなりませんが。
何を言っても認めてあげる、発言や思いをちゃんと受け入れる、自分のモノサシと比較して否定しない、そういう在り方をメンバー全員が持つこと。
涵養、という言葉は、今の社会にはなじまないのかもしれません。
社会には評価が蔓延していますから、評価されることへの耐性を誰もが持たねばなりません。
少年刑務所にいた少年たちが社会に出た時に持つべきものは評価への耐性ですが、自分は受け入れられたことがあるという事実が少年たちを支えるものになるはずです。
涵養という言葉が日本語にはある。そこに日本のやさしさを感じました。
涵養という言葉は社会にはなじまないかもしれない、しかし人を育てる、ヒントにはなるかも、と思っています。
ご登録いただくと、弊社の最新ニュースや弊社コンサルタントによるコラムなどをお届けします。
https://asian-identity.com/hr-egg-jp/subscribe
人事に関するご相談やお問い合わせはこちら。
https://asian-identity.com/hr-egg-jp/contact
Photo Credit : richard-rivas on unsplash
[content_block id=1636]