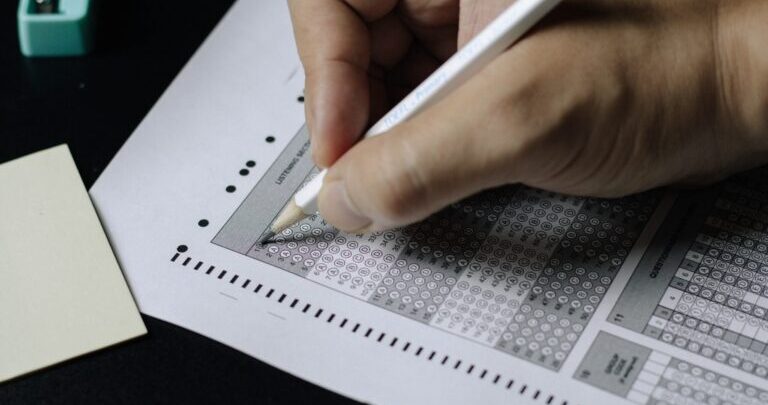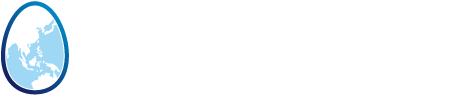HR Blog
HR Blog
曖昧さと厳密さ~MLBに思うルール設定の難しさ
2020年9月2日MLBのニュースを見るのが好きなのですが、最近MLBの「不文律(unwritten rules)」がよく話題になります。
「大差で勝ってるチームが盗塁してはいけない」などが代表的なものです。ルールブックには書いていませんが、マナーに反するからだそうです。こうしたマナー違反を犯すと、あとから報復でボールをぶつけられたりします。
日本以上にこういう不文律があるのがメジャーリーグだそうです。もちろん批判もあるようで、そんなものに従わなくてよいと反発する選手もいますが、古くから存在するこうした慣習はなかなかすぐには変わらないようです。
個人の記録もあるのですから、選手が全力を尽くすのは当たり前です。ルールがあいまいでは、全力でプレーしている選手がかわいそうです。誰から見てもはっきりとしたルールにした方が良いのではないかと個人的には思います。
これが日本の話ならまだしも、明確なルールを好みそうなアメリカにもこうした不文律があるのには驚かされます。
いわゆる「日本はハイコンテキスト(空気を読む)」アメリカは「ローコンテキスト(言語化する)」と言いますが、ことMLBに関しては逆の現象がおきているようです。
独自の文化の醸成には、「外界との交流の少なさ」が関係します。島国日本が豊かな文化を育み、またガラパゴス諸島で独自の生態系が生まれたのと、原理は同じです。
私の解釈では、野球はサッカーに比べて国際化が進んでいない(例えばオリンピックにはMLB選手は出場しませんよね)ので、たとえアメリカであっても、MLBという世界では独自のハイコンテキストな文化が形成されているということなのかな、と思います。
その一方で、こと契約となると、今度はガチガチに取り決めるのがMLBです。
今年絶好調の前田健太選手は、去年ドジャース時代には契約に苦しめられました。イニング数が増えると報酬が増えるという契約を結んでいたので、報酬を節約するためにせっかく好投していても短いイニングで交代させられた、と球団が批判の的となりました。
せっかく良いプレーをしてるのに契約のせいで続投できないのは本末転倒です。これはルールの厳格さが逆に足かせとなってしまっているケースです。ルールがあることで頑張らない方向にインセンティブがはたらくのは弊害以外の何物でもありません。
会社でも、時々「来年の目標が上がらないように、あえてギリギリで目標達成しておこう」ということがあったりします。一見悪い事ではなさそうですが、その評価指標が無ければ、本当はもっと会社は業績を伸ばせたかもしれません。評価指標のせいで「全力を尽くさない瞬間」を作ってしまってるとも言えます。
評価や報酬はその設計の仕方によって人の動きを明確にコントロールしますが、「頑張らない」方向にインセンティブが働かないよう、気を付けないといけません。
目標の数値化の重要性をよく耳にしますが、数字だけの評価には限界があると私は思っています。なぜなら、妥当な数値目標の設定というのは、本当に難しいからです。
しっかりプロセスを見える化したうえで、最終的には「人の判断」で評価する余地を残しておかないと、MLBのケースのように、数字が人間をコントロールしてしまう事が起こりかねません。
MBOやOKRなど様々な評価手法は出てきますが、「人が人を評価する」難しさは、昔からなにも変わってないように思います。
ルールは、曖昧すぎず、厳格すぎず。その適度なバランスを保つことにしか答えは見いだせないように思います。
ご登録いただくと、弊社の最新ニュースや弊社コンサルタントによるコラムなどをお届けします。
https://asian-identity.com/hr-egg-jp/subscribe
人事に関するご相談やお問い合わせはこちら。
https://asian-identity.com/hr-egg-jp/contact
[content_block id=1636]